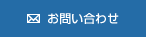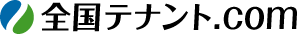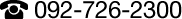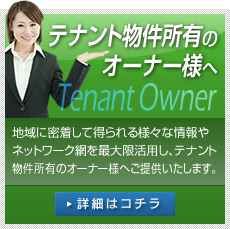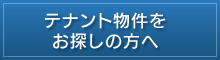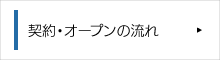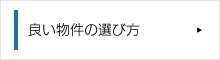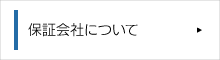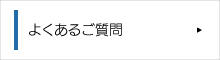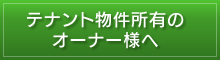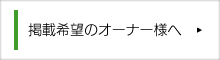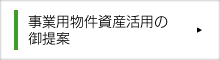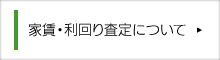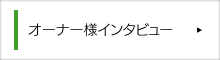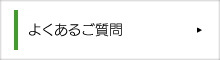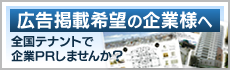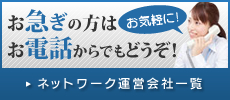全国テナント トップページ > 事業系賃貸トラブルの回避術
事業系賃貸トラブルの回避術
事例から弁護士に学ぶ!事業系賃貸トラブルの回避術
賃貸借契約のトラブルはその金額が高額化しやすいのが特徴です。契約書に印鑑を押す前でも、1億円を超える損害賠償の請求があるといった事例もあります。弁護士の田中さんが実際に相談を受けた事例を基に、あらかじめ知っておきたいポイントをチェックして、リスクに備えましょう。
事例.01
契約書に印鑑を押す前でも、1億6254万円の損害賠償
契約が決まらず、1億6254万円のトラブルに
大企業である「Y」は、グループ企業をすべてひとつの場所に集約しようとして、オフィスビルの賃貸を検討し始めました。賃料は月額3000万円。敷金だけでも4億円。仲介業にも気合いが入ります!
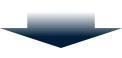
しかし「Y」の社内手続きがなかなか進まないため、5カ月が経過。その時点で申込書(契約書ではない)を受け取り、契約締結日を決めました。
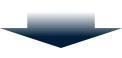
ところが、直前になって「Y」の会長が移転を承諾しないということに。会長の意見ひとつで、半年近くかけた交渉は白紙に戻りました。
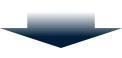
テナントのオーナー様は、さすがに納得がいきません。入居申し込み取り消しから、次のテナントが決まるまでの賃料、2億1000万円(3000万円×7カ月)の損害賠償を「Y社」に請求し、裁判所は1億6254万円の賠償を認めました。
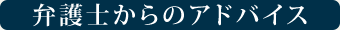
- 賃料など契約条件が折り合わなかった場合は責任を問えませんが、「会長が承諾しなかった」という内部的な事情は正当な理由にならず、責任を追及できるケースがあります。
- 契約書に押印する前でも損害賠償請求権が発生し、責任を追及できる場合があります。
- 契約を結ぶ前から内装工事の発注など、入居を目指してあらかじめ準備を進めるケースがあります。相手が入居しないとわかった時点で、すみやかに報告してもらいましょう。
事例.02
収益性に関する情報を、正確に説明せずに523万円の損害賠償
収益性に関する情報を正確に説明せず、523万円を支払い
今、流行のメディカルビル。ひとつのビルに薬局や複数の医院が入る形態です。そこでY不動産は、X小児科を勧誘し、合意書に調印。X小児科は内装工事の見積もりをスタートしました。
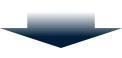
しかし、X小児科のほかに、メディカル系のテナントが決定する気配がありません。不安になったX小児科は、内装工事を遅らせ、進捗状況を見守っていました。
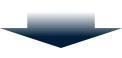
Y不動産は、入居をキャンセルされたくないので「他の医療機関3件から確約書をもらっています」と説明します。しかし、その説明がウソだったことが判明し、X小児科は入居をキャンセルします。
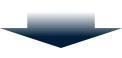
X小児科は、内装費用を含む1346万円の損害賠償を請求。判決では過失相殺も認められましたが、結果として、Y不動産は523万円の支払いを命じられました。
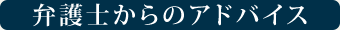
- 事業系テナントは、収益性に影響する情報が重要な説明義務の対象となります。
- 事業系テナントでは、工事費や移転費用、営業補償なども損害賠償の対象となるため、損害額が大きくなる傾向があります。
- 虚偽の説明をするのはもちろん、「知っていて告げない」ことも説明責任の違反になります。
事例.03
裁判官の主観で決まる?用法遵守義務違反の判決
裁判官の主観で決まる?用法遵守義務違反の判決
「不動産業」「広告業」としてテナントを紹介したが、実は、風俗店従業員用の性病検査を行っていた。
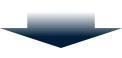
それを知ったテナントのオーナー様は、テナント契約を解除したうえで、用法義務違反で訴えることになりました。
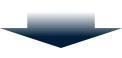
判決は「一般人からは強い警戒心や忌避の感情を喚起せしめないではおかれない性質の行為であるから、賃貸人にとって誠に遺憾なことである。その約定違反の程度は極めて重大かつ悪質」として、用法遵守義務違反を認めました。
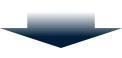
しかし、このようにデリケートな問題は、人によって受け取り方がさまざま。ほかの裁判官ならば、用法遵守義務違反を否定した可能性もあります。
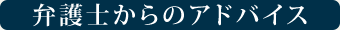
- 用法遵守義務違反の判断要素は、具体的にオーナーさまにどのくらい不利益があったのかが問われます。
- 今回の事例の判決はオーナー様側が勝ちましたが、どちらの判決もあり得ます。
事例.04
用法に記載のない事業でも、契約解除にならないケースも
用法に記載のない事業でも、契約解除にならないケースも
事例③の逆パターンの事例です。活字を組んで印刷をする「活版印刷」を用法として、賃貸契約を結びました。
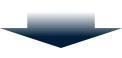
しかし、数年後、「活版印刷」をやめて「インクジェット」の印刷所にリニューアルしました。
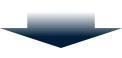
インクが飛び散りにくい「インクジェット」の印刷所ならば、建物が傷みにくいとテナントのオーナー様に喜ばれました。
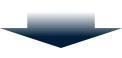
このような例は、双方にとって良い事例です。しかし、「寿司店」が「焼肉屋」に変わるなどの事例では、脂の飛び散りや汚れが倍増する可能性があるので、用法遵守義務違反を問われる場合があります。
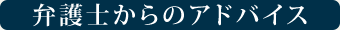
- 「事務所」「店舗」「飲食店店舗」などと記述するのは、目的が広範囲になってしまうので避けましょう。
- 契約書の目的は具体的に特定しましょう。
例:「不動産仲介業の事務所」「女性用服飾雑貨の販売店舗」「寿司店」「サンドウィッチおよびこれに通常付随するサイドオーダー(ただし、調理の際に火を使用するものを除く)を提供する飲食店」など。
事例.05
オーナー様に有利な、業務委託契約
いつでもテナント契約を解除できる、業務委託契約
テナントビル内の店舗とは「事業系賃貸借」でなく「業務委託契約」を結んでいました。
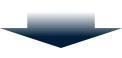
「事業系賃貸借」だけだと、正当な理由がなければ契約は解除できません。しかし「業務委託契約」を結んでいると、「借地借家法」の適用とならず、いつでも契約を解除できます。
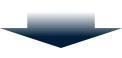
テナントの売り上げが悪い場合や、ビル全体の雰囲気にそぐわない場合は、その旨を伝えて改善してもらうことができます。また改善がなされない場合は、テナントオーナーさんの意思によって契約解除ができます。
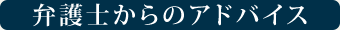
- 賃貸借契約だけでなく、オーナー様に有利な「業務委託契約」の利用も検討しましょう。
- 業務委託契約の場合、店舗とは独立した出入り口を設けることなどは避けて、店舗のレイアウトを作る際に、独立させすぎないようにしましょう。百貨店の中に入居しているテナントのイメージです。
- 内装工事などに関与し、営業報告や営業会議を定期的に行いましょう。
- 資料などで証拠として残しておきましょう。
事例.06
中途解約条項を記載せず、367万円を支払い
中途解約条項を記載せず、367万円を支払い
借主から「建て増しをしてくれるなら物件を借りたい」との申し出がありました。テナントのオーナー様は3300万円をかけて建て増しを実施。9年間は入居する予定と聞かされ、それならば賃料で建て増し料金を補えると考えての決定でした。
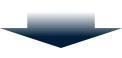
ところが、○年後に借主より解約の申入れがありました。しかも、仲介業者の用意した契約書には、借主が中途解約した際の条項が入っていませんでした。
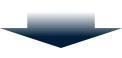
オーナー様は仲介業者に対して、残りの賃料を払ってほしいという請求をしました。
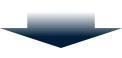
裁判所は仲介業者には損害賠償の責任があるが、オーナー様にも落ち度があるとして請求額の約6割である367万円の賠償を認めました。
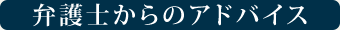
- 契約の種類によって注意すべき点があります。
- 「通常入っているべき条項」をしっかり確認しましょう。

代表パートナー弁護士・弁理士
田中雅敏さん
明倫国際法律事務所 http://www.meilin-law.jp/
賃貸に関する相談を受けて、福岡で15年。テナント系も住居系もあつかう、問題解決のプロフェッショナルです。